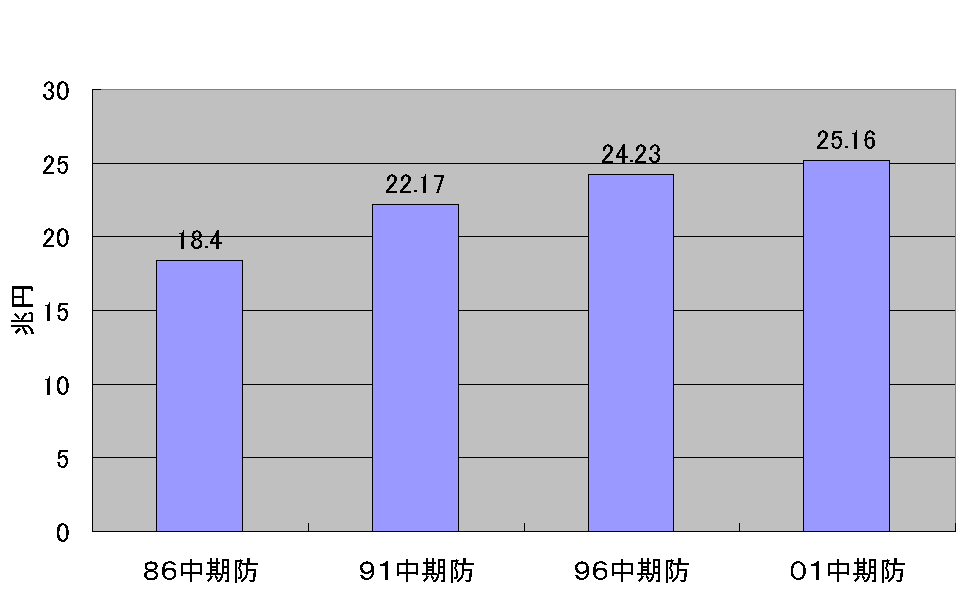 |
岡山県平和委員会情報
岡山県教職員組合の「岡山の平和教育 第16号」(1998年5月発行)に岡山県平和委員会会長の中尾元重さんがまとめられた「新ガイドラインと岡山県」に引き続き、2001年5月発行の「岡山の平和教育 第19号」にまとめられた県内情勢です。
防衛庁は、1976年に制定した軍拡の指針「防衛計画の大綱」(旧大綱)を、ソ連の崩壊など国際情勢の新たな変化を受けて改め、1995年11月に「平成8年度以降に係る防衛計画の大綱について」(新大綱)を決めました。
自衛隊は、すでにその段階で「日本は自国の軍隊を引き続きアメリカの装備、要領、訓練、整備、兵站に従事させることによって、アメリカの作戦に直接貢献している」(「日米安保関係報告」米国防総省95年3月)と高く評価されていましたが、この新大綱で「我が国周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合」は、「日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用を図ること等により適切に対応」することなどをあげ、海外派兵体制の構築を公然と掲げました。
この新大綱に基づいて政府は、96年度から2000年度までに達成すべき軍拡目標を「中期防衛力整備計画」(96中期防)として定めました。この計画は途中、バブル崩壊による見直しで若干の減額修正をしましたが、輸送艦「おおすみ」の建造など総額24兆2300億円の経費を注ぎ込んで、今年3月末に終了しています。
その最終結果はまだ公表されていませんが、計画の99%を達成した昨年3月末現在、自衛隊は陸海空自衛官23万6,821人、戦車1,070両、護衛艦55隻19万2,000トン、F15戦闘機203機、対潜哨戒機100機などを保有する強力な武装集団に成長しています(2000年版防衛白書)。52年前、アメリカの圧力で日本国憲法を蹂躙して生まれた警察予備隊は、いまや世界第一級の実力を備える軍隊に変貌してしまいました。
この96中期防の5年間は、日米安保共同宣言(96年)から、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)の見直し(97年)、周辺事態法等戦争法の制定(99年)と突き進む異常な5年間であり、一方で地方分権一括法、盗聴法、国旗・国歌法の制定など、参戦に備えて有事法制を志向する反動化が自自公政権のもとで急速に整備されるという、憲政史上かつてない重大な転換期と重なりました。
しかし、政府は新ガイドラインに沿った新大綱の軍拡を進めるために2000年12月15日、安全保障会議と閣議を開いて、さらに2001年度から始まる新たな5年間の01中期防を決定しました。決定にあたってはアメリカのQDR(4年ごとの国防計画の見直し)との整合性を図るため、「ペンタゴン(米国防総省)と防衛庁との間で、課長クラスの専門家会合が設置され、その密接な協議を経て策定された」(「ピースかながわ」安保ウォッチング・松尾高志http://www.peace-kanagawa.org/)という事実が明らかになっています。その結果01中期防全体がアメリカの強い軍事分担の要求にこたえるものとなりました。その第四章には「日米安全保障体制の信頼性の向上を図るための施策」として、「我が国に対する武力攻撃に際しての共同作戦計画についての検討及び周辺事態に際しての相互協力計画についての検討を含む日米共同作業を推進」(傍線は筆者)することが盛り込まれました。共同作戦計画も相互協力計画も新ガイドラインで合意された日米共同の戦争計画であり、これまで数次にわたるどの中期防も言い出せなかったものです。このような戦争計画の策定が憲法のもとで閣議決定されたのは史上初めてのことであり、事態は極めて重大と言わなければなりません。
こうして決定された01中期防の規模は25兆1600億円となりました。96中期防の24兆2300億円より9300億円(3.8%)も多く、80年代後半の86中期防(86年度~90年度)の18兆4000億円に比べると実に36.7%増、総額で6兆7600億円も上回る額となります。(図1)
図1 中期防衛力整備計画の総額の推移
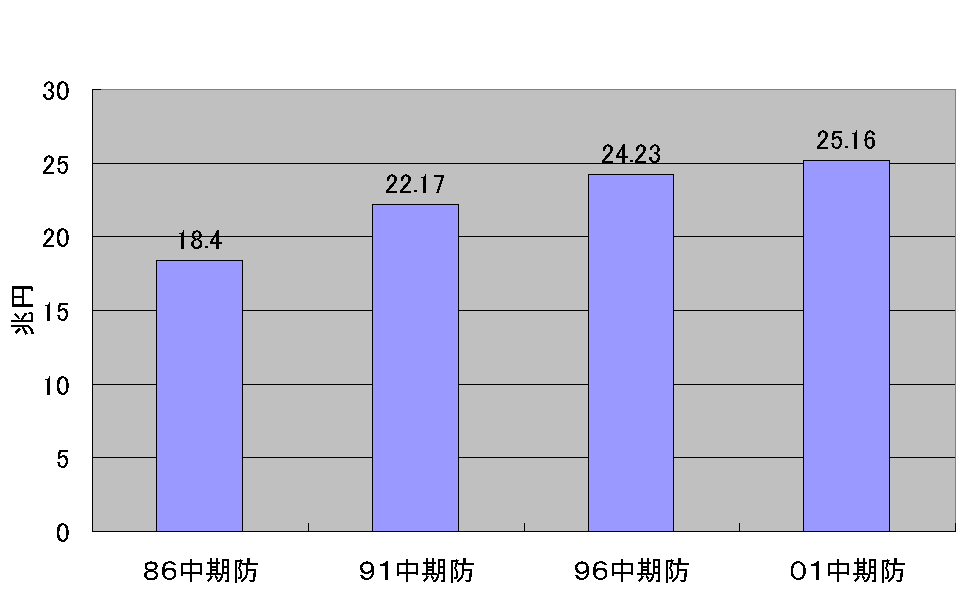 |
この膨大な軍事費で防衛庁は、アメリカの要求のままに自衛隊の「周辺事態」対応能力の一層の充実を図り、海外での米軍との共同作戦に備えることを目指しています。
| 区 分 | 種 類 | 整備規模 |
| 陸上自衛隊 | 戦車 | 91輌 |
| 火砲(迫撃砲除く) | 47輌 | |
| 多連装ロケットシステム | 18輌 | |
| 装甲車 | 129輌 | |
| 戦闘ヘリコプター | 10機 | |
| 輸送ヘリコプター(CH-47JA) | 7機 | |
| 地対空誘導弾(ホーク)改善用装備品) | 0.25個群 | |
| 新中距離地対空誘導弾 | 1.25個群 | |
| 海上自衛隊 | 護衛艦 | 5隻 |
| 潜水艦 | 5隻 | |
| その他 | 15隻 | |
| 自衛艦建造計 | 25隻 | |
| (トン数) | (約8.6トン) | |
| 哨戒ヘリコプター(SH-60J及びSH-60改) | 39機 | |
| 新掃海・輸送ヘリコプター | 2機 | |
| 航空自衛隊 | 要撃戦闘機(F-15)近代化改修 | 12機 |
| 支援戦闘機(F-2) | 47機 | |
| 輸送ヘリコプター(CH-47J) | 12機 | |
| 空中給油・輸送機 | 4機 |
陸海空各自衛隊の整備計画は表1のとおりです。紙数の関係で詳しくは述べられませんが、陸では七四式戦車の退役に備えて九〇式戦車を小型化した新型戦車の開発に取り組み、対戦車用戦闘ヘリコプターなどを増備します。海では1隻950億円もする排水量1万3500トンのヘリ搭載型護衛艦を2隻建造する予定です。1万トンを超える自衛艦はこれが初めてで、軽空母を目指すものとさえいわれています。アメリカの戦域ミサイル防衛(TMD)に組み込む新型イージス護衛艦も2隻建造します。空では遂に空中給油機が導入(4機)されることになりました。かつて70年代には政府自身が「周辺諸国の、領海、領空深くはいっていけるものは、許容されざる足の長さ」とし、その保有を認めなかった代物です。また、現在のC1輸送機の後継機として、その3倍の能力を備えた航続距離6500㌔、最大積載量約26㌧の大型長距離輸送機の開発も盛り込みました。
部隊編成では、「核・生物・化学兵器による攻撃(NBC攻撃)等各種の攻撃形態への対処能力の向上を図る」ことを決めました。自衛隊は創設以来米軍の指導のもとにNBC戦対処訓練を重ねていますが、アメリカの強い圧力を受けて2000年度予算に24億円の本格的なNBC関連経費を計上し、今年度はそれを29億円に増額しました。今年3月には、東京世田谷区の陸上自衛隊三宿駐屯地にNBC兵器に対処する専門部隊=開発実験団部隊医学実験隊を新たに編成したのを始め、2001年度からは師団・旅団の化学防護隊の強化に踏み切ります。
これらの装備・研究開発は、いずれも新ガイドラインのもとでアジア諸国から中東へ海外出動することを前提にして初めてその意味を持つものばかりです。朝鮮半島や東南アジアに広がっている平和の流れに逆行するこの大軍拡が、近隣諸国に大きな脅威をもたらすことになるのは余りにも明らかであると言わなければなりません。
以下、このような状況と深く関連する県内の新しい問題を、本誌第16号(1998年5月)の拙稿「新ガイドラインと岡山県」となるべく重複しないように簡記しておきます。
(一)日本原駐屯地
96中期防で1999年3月29日、定員7100人の第13師団が定員4100人の第13旅団に改編されました。第13旅団は、新大綱が目標としている陸上自衛隊8個師団6個旅団の体制を目指して最初に編成替えを行った組織で、「中国地方の特性を踏まえ、地上及び空中機動能力や情報収集機能の強化を図ること」(「99年版防衛白書」)を目的としたコンパクトな「陸上機動旅団」です。
それに伴って日本原駐屯地の部隊も第13特科隊、第13高射特科中隊、第13戦車中隊及び業務隊に編成され、現在約740人程度が常駐していると見られます。
配備されている主な武器は、155㍉榴弾砲(FH70)、81式短距離地対空誘導弾(短SAM)、93式近距離地対空誘導弾(近SAM)、74式戦車、高機動車などで、かつての105㍉榴弾砲や61式戦車など旧式の兵器は姿を消し、近代化され機動力に富んだ高性能兵器が数多く導入されています。
今年度は、陸上自衛隊が毎年6月から8月の時期に行っている北方機動演習を第13旅団と四国の第2混成団(善通寺)が実施する予定で、旅団編成化した日本原の部隊も参加するはずです。この北方機動演習は1カ月以上に及ぶ師団規模の実動演習で、北海道の矢臼別演習場までの長距離を移動する列島縦断の訓練もかねます。またこの演習は自衛隊だけでなく、民間のフェリーや鉄道なども数千人の部隊や武器弾薬の輸送に「動員」される大掛かりなものです。周辺事態法で定めた有事に対する「国以外のものによる協力」を先取りする演習でもあり、注意と監視が要求されます。
| 日本原駐屯地の74式戦車 |
(二)日本原演習場
勝田郡奈義町と勝北町にまたがる日本原演習場は、1952㌶で、陸上自衛隊の中規模演習場14カ所のうち6番目の広さです。大部分は奈義町に広がり、奈義町の約24%を占めています。
奈義町に届けられた演習の実施計画書によると、日本原演習場は主に中部方面隊の各部隊が演習場を使用しており、ピーク時の97年には年間303日、そのうち実弾演習は延べ127日に及び、演習参加人員も延べ11万人に達しています。演習場内での実弾の使用総数は98年に約11万発、99年に約13万2000発でした。演習日1日平均1400発に相当する規模です。最近では110㍉個人携帯対戦車弾の演習が急増し、98年に33回3337発、99年は25回で4331発の実弾が発射されています。
演習の様相も次第に変化しています。ヘリコプターの低空飛行と夜間飛行訓練が増加し、戦車の夜間走行や、防毒マスクを着けた訓練も目撃されるようになりました。
(三)警戒すべき日米共同演習
一方で日本原の部隊や隊員は饗庭野(滋賀県)などの日米共同演習に参加しており、日米共同作戦に対する能力を次第に蓄積していると見られます。日本原演習場も全国で広がっている日米共同使用の演習場にならないという保障は全くありません。自衛隊施設の日米共同使用は、日米地位協定二条4項bの規定によるもので、国会も自治体も全く関与できない日米合同委員会の密室協議で決められます。その数は中曽根内閣時代から急増し、1982年に8カ所であったものが、99年度末には44カ所に広がりました。すでに日本原演習場より小さい自衛隊の新潟県高田関山演習場や群馬県相馬原演習場が米軍との共同演習場として使われています。日本原には終戦後の1946年3月から連合軍が進駐し、1950年に始まった朝鮮戦争下で米軍の激しい実弾演習が行われ、町民が多くの被害を受けた歴史がありますが、新ガイドラインのもとでその悪夢がよみがえる条件は非常に強くなっています。
折りも折り昨年12月、奈義町議会で町長に日米共同演習の受け入れを促す質問が行われました。これは奈義町議会始まって以来のことで、その意味を軽視することはできません。
岡山市宿の陸上自衛隊三軒屋駐屯地には、三軒屋弾薬庫と呼ばれている関西地区補給処三軒屋弾薬支処の他、第350施設中隊、第312基地通信中隊三軒屋派遣隊、第116地区警務隊三軒屋連絡班が置かれています。1993年2月の防衛庁国会提出資料によると面積は202.5ヘクタールで約250名の隊員がいることになっています。
三軒屋弾薬支処は中部方面隊関西地区補給処(宇治市)の直属部隊で、弾薬の貯蔵と在庫管理、搬入・搬出の業務、弾薬の処理などにあたっています。
岡山県平和委員会の調査によると、駐屯地内には少なくとも8カ所の地下弾薬庫があることが確認されています。そのうち4カ所の入り口に数字の1を表示した八角形のプレート(①標識)が立ててあります。
この標識は、米軍に準拠したもので、最も危険な大爆発を起す火薬類を貯蔵していることを示しています。米国防総省弾薬・爆発物類安全基準によれば、①標識の弾薬庫とは、「事故が起きた場合は消火活動に関係ないものは2000フィート(約600メートル)以上離れなければならない。この弾薬が45トンを超えるときは周辺に住居を建ててはならない」ものとされています。陸上自衛隊は1978年11月のガイドライン以降、この米軍の基準に準じて弾薬庫の危険度を表示するようになり、三軒屋には1981年1月からこの①標識が立てられてきました(岡山市議会八九年三月十日答弁)。しかし三軒屋駐屯地周辺には、このような爆発の危険を知らされないまま、弾薬庫から500メートル以内に半田山ハイツや津高台団地などの住宅が隣接しています。
第350施設中隊は戦場の最前線に出て侵入路や陣地を構築し、地雷を敷設するなどの任務を持ちます。また、第312基地通信中隊三軒屋派遣隊は金甲山に通信施設を設置しています。この金甲山のアンテナには隊舎から敷地内の山頂にある反射版を介してマイクロ波回線がつながっています。
実は戦争法が公布施行された1999年の12月8日、この三軒屋に米太平洋陸軍兵站部長・ダニエル大佐以下六人が来ています。日米兵站連絡会議のプログラムによる中部方面隊の兵站施設研修というのがその目的で、この研修には自衛隊側から陸幕装備部副部長や中部方面隊の後方運用課長ら八人が参加しました。弾薬庫は日米新ガイドライン・戦争法が発動されるとき、兵站作戦の中枢を占めます。そのときに備えて三軒屋の機能点検と整備が日米双方で行われたと見なければなりません。
| 三軒屋駐屯地正門 |
いま備前市福石、和気町木倉、寄島町鉢山の県内3カ所で自衛隊の防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の建設が進められています。このアンテナ施設が完成すると、IDDNの太平洋側ルートのうち兵庫県赤穂市の黒蔵山中継所(既存施設)→備前市福石→和気町木倉→金甲山(前記アンテナ)→寄島町鉢山→広島県と伸びる岡山県内のルートが出来上がることになります。
このIDDNについて、私は本誌第十六号で次ぎのように指摘しておきました。
「IDDNはもともと自衛隊と米軍の相互運用性を基本としているので、その基地の機能は米軍と共用されることになろう。IDDNが完成すると、例えば最前線の戦車や護衛艦に積み込んだIDDN端末の「可搬型地球局」(衛星通信の送受信アンテナを搭載した装置)によって、陸上、海上の戦闘場面が直接中央指揮所に伝達され、その情報はリアルタイムで米軍の作戦司令部にも送信される。またIDDNは、周辺有事で米軍が出撃するときの作戦・補給に関する膨大な情報処理を後方で支える役割も果たすだろう。」
「県内に計画されているIDDN無線中継所は明らかにセミ米軍基地というべき危険なものである。」
このIDDN建設計画は、前九六中期防で引き続き整備を推進するとされていましたが、新しい01中期防では「民間の情報通信技術の発展を踏まえて防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備を完了する」とされました。実際には2003年度末の完成を目指しており、この方針に基づいて2001年度予算では113億円の整備費を計上しています。県内の建設工事も大きく進むと思われます。
IDDN建設場所(2001年1月) |
「わが国には護衛艦、潜水艦などの艦艇メーカーが7造船所、掃海艦艇などの艦艇メーカーが4造船所、それに加えて支援船などのメーカーが20社を超えて存在している」(「世界の艦船」1997年3月号)といわれます。その中で三井造船㈱は、三菱重工業、石川島播磨重工業、住友重機、日立造船などとともに護衛艦建造のカルテルを形成している造船メーカーです。
三井造船㈱玉野事業所(以下三井玉野)は、1953年の第16特別国会で自衛艦の建造が承認されるといち早く三菱重工業などとともに護衛艦の建造に着手し、以来、日本再軍備を艦艇部門で推進する中心的役割を果たしてきました。
三井玉野で最初に建造した護衛艦「いなづま」(1070㌧)は乙型警備艦と呼ばれ、1954年12月に着工し1年2カ月余りの工程で竣工しています。それから潜水艦救難艦「ちはや」(5450㌧)が海上自衛隊に引き渡される2000年3月までの45年間に、ここで建造された自衛艦は中型護衛艦(DE)12隻(21650㌧)、大型護衛艦(DD)8隻(18200㌧)、潜水艦救難母艦(AS)1隻、潜水艦救難艦(ASR)1隻、音響測定艦(AOS)2隻、掃海母艦(MST)1隻、輸送艦(LST)1隻、計26隻に上ります(表2)。
国内では1954年から今年3月までに中型護衛艦(DE)が27隻(41680㌧)、大型護衛艦(DD)が68隻(224890㌧)建造されました。この中で三井玉野は中型護衛艦の建造では他社を圧倒して隻数で44%、トン数で52%を建造したことになります。それに比べて大型護衛艦の受注は隻数で12%、トン数で8%しかありません。しかし最近は、自衛艦最大級の輸送艦「おおすみ」(8900㌧)や掃海母艦「ぶんご」(5700㌧)、潜水艦救難艦「ちはや」(5400㌧)など、外洋作戦に備えて従来の同型艦を一挙に大型化した艦艇が建造されているのが特徴です。
現在玉野の造船所では27隻目にあたる輸送艦の「おおすみ」型2番艦を建造中で、昨年11月に進水し、「しもきた」と命名されました。来年3月に竣工する予定です(「おおすみ」については本誌第16号を参照)。
実は、この「おおすみ」も「しもきた」も自衛隊艦艇史上2回目のネーミングなのです。初代の「おおすみ」と「しもきた」は1961年4月にアメリカから供与された輸送艦(1650㌧)に付けられていました。この二隻の輸送艦は日米防衛相互援助協定(MSA協定)に基づいて米本国でモスボールされていたのを供与されたもので、すでに1974年3月と翌75年3月にそれぞれ退役しています。
| 三井玉野で進水後ぎ装中の「おおすみ」 |
表2 三井造船(株)玉野事業所で建造された自衛隊艦艇一覧
(自衛隊装備年鑑2000年度版による)
| No. | 計画年度 | 艦名 | 記号 | 艦番号 | 排水量(t) | 起工 | 進水 | 竣工 | 型式 | 記事 |
| 1 | 53 | いなずま | DE | 203 | 1,070 | 54.12.25 | 55.08.04 | 56.03.05 | いかずち型 | 除籍艦艇 |
| 2 | 55 | しきなみ | DD | 106 | 1,700 | 56.12.24 | 57.09.25 | 58.03.15 | あやなみ型 | |
| 3 | 57 | たかなみ | DD | 110 | 1,700 | 58.11.08 | 59.08.08 | 60.01.30 | あやなみ型 | |
| 4 | 59 | いすず | DE | 211 | 1,490 | 60.04.16 | 61.01.17 | 61.07.29 | いすず型 | |
| 5 | 62 | やまぐも | DD | 113 | 2,050 | 64.03.23 | 65.02.27 | 66.01.29 | やまぐも型 | |
| 6 | 65 | みねぐも | DD | 116 | 2,150 | 67.03.14 | 67.12.16 | 68.08.31 | やまぐも型 | |
| 7 | 67 | ちくご | DE | 215 | 1,470 | 68.12.09 | 70.11.03 | 70.07.31 | ちくご型 | |
| 8 | 68 | みくま | DE | 217 | 1,470 | 70.03.17 | 71.02.16 | 71.08.26 | ちくご型 | |
| 9 | 69 | とかち | DE | 218 | 1,470 | 70.12.11 | 71.11.25 | 72.05.17 | ちくご型 | |
| 10 | 70 | いわせ | DE | 219 | 1,470 | 71.08.06 | 72.06.29 | 72.12.12 | ちくご型 | |
| 11 | 71 | によど | DE | 221 | 1,470 | 72.12.12 | 73.08.28 | 74.02.08 | ちくご型 | |
| 12 | 72 | よしの | DE | 223 | 1,500 | 73.09.28 | 74.08.22 | 75.02.06 | ちくご型 | 就役艦艇 |
| 13 | 73 | のしろ | DE | 225 | 1,500 | 78.01.27 | 76.12.23 | 77.06.30 | 改ちくご型 | |
| 14 | 77 | いしかり | DE | 226 | 1,290 | 79.05.17 | 80.03.18 | 81.03.28 | いしかり型 | |
| 15 | 79 | はまゆき | DD | 126 | 2,950 | 81.02.04 | 82.05.27 | 83.11.18 | はつゆき型 | |
| 16 | 81 | ちよだ | AS | 405 | 3,650 | 83.01.19 | 83.12.07 | 85.03.27 | ちよだ型 | |
| 17 | 82 | せとゆき | DD | 131 | 3,050 | 84.01.16 | 85.07.03 | 86.12.11 | はつゆき型 | |
| 18 | 84 | やまぎり | DD | 152 | 3,500 | 86.02.05 | 86.10.08 | 89.01.25 | あさぎり型 | |
| 19 | 86 | あぶくま | DE | 229 | 2,000 | 88.03.17 | 88.12.21 | 89.12.12 | あぶくま型 | |
| 20 | 87 | おおよど | DE | 231 | 2,000 | 89.03.08 | 89.12.19 | 91.01.23 | あぶくま型 | |
| 21 | 89 | ひびき | AOS | 5201 | 2,850 | 89.11.28 | 90.07.27 | 91.01.30 | ひぴき型 | |
| 22 | 90 | はりま | AOS | 5202 | 2,850 | 90.12.26 | 91.09.11 | 92.03.10 | ひぴき型 | |
| 23 | 92 | はるさめ | DD | 102 | 4,550 | 94.08.11 | 95.10.16 | 97.03.24 | むらさめ型 | |
| 24 | 93 | おおすみ | LST | 4001 | 8,900 | 95.12.06 | 96.11.18 | 98.03.11 | おおすみ型 | |
| 25 | 95 | ぶんご | MST | 464 | 5,700 | 96.07.04 | 97.04.24 | 98.03.23 | うらが型 | |
| 26 | 96 | ちはや | ASR | 403 | 5,450 | 97.10.13 | 98.10.08 | 00.03.23 | ちはや型 | |
| 27 | 98 | しもきた | LST | 4002 | 8,900 | 99.11.30 | 00.11.29 | 02.03.-- | おおすみ型 | 建造中 |
| <参考> 艦艇の種別と記号 | ||||||||||
| 艦艇種別 | 記号 | 意 味 | ||||||||
| 護衛艦(中型) | DE | Destroyer,Escort | ||||||||
| 護衛艦(大型) | DD | Destroyer (イニシャルが1字のときは重複させる) | ||||||||
| 潜水艦救難母艦 | AS | Auxiliary Submarine tender | ||||||||
| 音響測定艦 | AOS | Auxiliary Ocean Survey | ||||||||
| 輸送艦 | LST | Landing Ship,Tank | ||||||||
| 掃海母艦 | MST | Mine Sweeper Tender | ||||||||
| 潜水艦救難艦 | ASR | Auxiliary Submarine Rescue | ||||||||
県北の中国山地一帯で、いまも無法な米軍機の低空飛行訓練が続いています。その実態の一部や、安保条約の日米地位協定にさえ違反する違法性については本誌第16号で報告しましたが、現在もその状況に本質的な変化は見られません。異常な主権侵害そのものであるこの低空飛行訓練について日本政府は、「具体的なルートの詳細等は、米軍の運用にかかわる問題であり、承知しておらず、また、これからも事前に明らかにするよう米側に求める考えはない」(秋葉忠利衆議院議員の質問趣意書―98年10月―に対する政府回答)とする態度に終始し、日米地位協定に基づく日米合同委員会も1999年1月、「戦闘即応体制を維持するために必要とされる技能の一つが低空飛行訓練であり、これは日本で活動する米軍の不可欠な訓練所要を構成する」という合意書を公表しています。
しかし、広島県では君田村などが1997年に「米軍の低空飛行の即時中止を求める県北連絡会」を結成し、自治体と住民が一体となって抗議運動を始めました。これを契機に低空飛行の騒音被害を受けている全国の自治体が手を携えて立ちあがり、「米軍機の低空飛行訓練などの被害関係者全国交流会」も1998年8月と昨年4月の2回にわたって開催されるまでになりました。広島県議会も一九九八年、全会一致で低空飛行訓練の即時中止を求める決議を採択しています。岡山県でも1994年以来、低空飛行訓練の自粛を米軍に求めるよう、外務省に対して行政レベルの要請を続けています。
このような状況の中で、今年2月までに、岡山県が地方振興局をとおして市町村から報告を受けた低空飛行の目撃機数は表3のとおりです。これによると1998年に一旦沈静化しそうになった低空飛行がその後再び増加していることを示しており、2000年度は55機が目撃されています。
しかし、この統計は、前にも指摘したように正確な実態調査ではなく、およその傾向を表わしているに過ぎません。過疎地域の出来事ということもあって目撃報告数もその町村も限られています。
今後、行政に積極的な調査と抗議を要求するとともに、教育現場も含めて米軍機の主権侵害を告発し、住民の証言と被害の実態を記録する運動を起すことが求められていると言えます。
| 中国山地を低空飛行するF/A18(県北連絡会パンフより) |
表3 岡山県内米軍機低空飛行目撃機数(岡山県の調査による)
| 年 度 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 低空飛来機数 | 170 | 125 | 96 | 36 | 19 | 41 | 55 |
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 低空飛来機数合計 | 18 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 大佐町 | 5 | 5 | |||||||||||
| 湯原町 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 23 | |||||||
| 美甘村 | 1 | 1 | |||||||||||
| 富村 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上斎原村 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |