 |
(写真1)三井造船玉野事業所で艤装中の「おおすみ」 |
2003年12月 岡山県平和委員会
このパンフレットは、1998年5月発行の岡山県教職員組合の研究雑誌「岡山の平和教育第16号」に岡山県平和委員会会長の中尾元重氏が寄稿した「新ガイドラインと岡山県」に引き続き、2001年5月発行の「岡山の平和教育第19号」に最新の県内情勢のポイントをわかりやすくまとめた「自衛隊の新軍拡計画と岡山県」をもとにして、有事関連3法が成立した情勢のもとで、ブッシュ戦略と新ガイドラインが求める自衛隊海外派兵と有事態勢が進められているなかでの岡山県内の自衛隊の動きをまとめたものです。
1.
海外派兵態勢づくりと有事法制
朝鮮戦争の開始直後、1950年7月8日のマッカーサーの指示にもとづいて始まった日本の再軍備は「警察予備隊」から「保安隊」を経て1954年7月に「自衛隊」となり、以後一貫して米軍の補完、支援戦力として強化されてきました。創設50周年となる自衛隊は、新ガイドラインのもとで制定された周辺事態法、有事関連3法などに基づいて海外派兵と有事対応態勢の構築に向けた整備を次々に推進しています。
(1)新「防衛計画の大綱」と中期防衛力整備計画
防衛庁は、1976年に制定した軍拡の指針「防衛計画の大綱」(旧大綱)を、1991年のソ連崩壊や湾岸戦争など国際情勢の新たな変化を受けて改め、1995年11月に「平成8年度以降に係る防衛計画の大綱について」(新大綱)を決めました。
自衛隊は、すでにその段階で「日本は自国の軍隊を引き続きアメリカの装備、要領、訓練、整備、兵站に従事させることによって、アメリカの作戦に直接貢献している」(「日米安保関係報告」米国防総省95年3月)と高く評価されていましたが、この新大綱で「我が国周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合」は、「日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用を図ること等により適切に対応」することなどをあげ、海外派兵態勢の構築を公然と掲げました。
この新大綱に基づいて政府は、1996年度から2000年度までに達成すべき軍拡目標を「中期防衛力整備計画」(96中期防)として定めました。
この計画は途中、バブル崩壊による見直しで若干の減額修正をしましたが、輸送艦「おおすみ」の建造など総額24兆2300億円の経費を注ぎ込んで、2001年3月末に終了しています。
 |
(写真1)三井造船玉野事業所で艤装中の「おおすみ」 |
その結果2001年3月末現在、自衛隊は陸海空自衛官23万6,821人、戦車1,070両、護衛艦55隻19万2,000トン、F15戦闘機203機、P3C等哨戒・情報収集機100機などを保有する強力な武装集団に成長(2000年版防衛白書)し、アメリカの圧力で日本国憲法を蹂躙して1950年に生まれた警察予備隊は、いまや世界第一級の実力を備える軍隊に変貌してしまいました。
この96中期防の5年間は、日米安保共同宣言(1996年)から、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)の見直し(1997年)、周辺事態法等戦争法の制定(1999年)と突き進む異常な5年間であり、一方で地方分権一括法、盗聴法、国旗・国歌法の制定など、海外参戦に備えて有事法制を志向する反動化が自自公政権のもとで急速に整備されるという、憲政史上かつてない重大な転換期と重なりました。
そして、政府は新ガイドラインに沿った新大綱の軍拡を進めるために2000年12月15日、安全保障会議と閣議を開いて、2001年度から始まる新たな5年間の01中期防を決定しました。
決定にあたってはアメリカのQDR(4年ごとの国防計画の見直し)との整合性を図るため、「ペンタゴン(米国防総省)と防衛庁との間で、課長クラスの専門家会合が設置され、その密接な協議を経て策定された」(「ピースかながわ」安保ウォッチング・松尾高志http://www.peace-kanagawa.org/)という事実が明らかになっています。
その結果01中期防全体がアメリカの強い軍事分担の要求にこたえるものとなりました。その第四章には「日米安全保障体制の信頼性の向上を図るための施策」として、「我が国に対する武力攻撃に際しての共同作戦計画についての検討及び周辺事態に際しての相互協力計画についての検討を含む日米共同作業を推進」することが盛り込まれました。
共同作戦計画も相互協力計画も新ガイドラインで合意された日米共同の戦争計画であり、これまで数次にわたるどの中期防も言い出せなかったものです。
このような戦争計画の策定が憲法のもとで閣議決定されたのは史上初めてのことです。
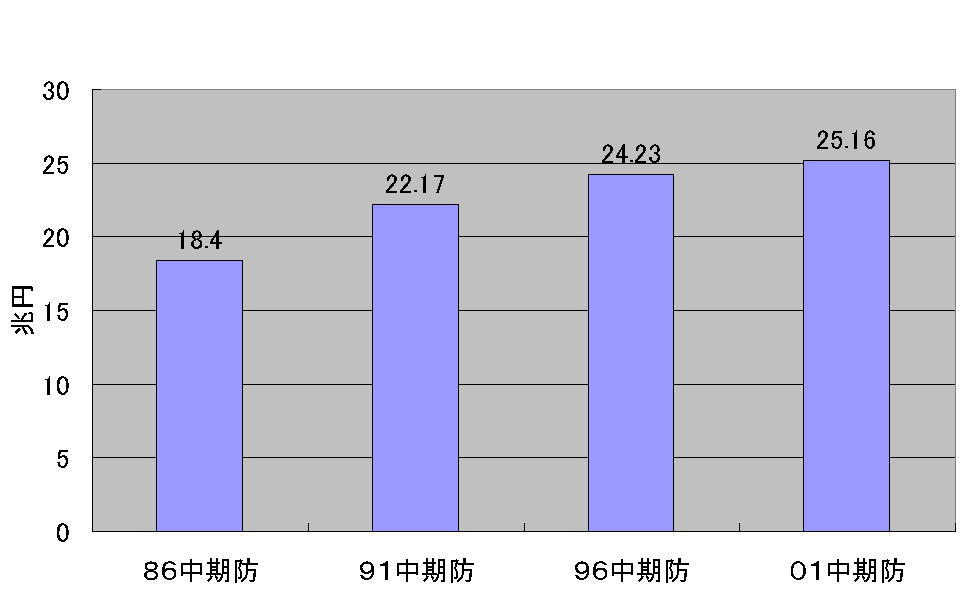 |
(図1) 中期防衛力整備計画の総額の推移 |
こうして決定された01中期防の規模は25兆1,600億円となりました。
96中期防の24兆2,300億円より9,300億円(3.8%)も多く、80年代後半の86中期防(86年度~90年度)の18兆4,000億円に比べると実に36.7%増、総額で6兆7,600億円も上回る額となります。(図1参照)
この膨大な軍事費で防衛庁は、アメリカの要求のままに「周辺事態」から「武力攻撃事態」への自衛隊の対応能力を一層充実させ、朝鮮半島や台湾付近をはじめとする世界中でのアメリカの先制武力攻撃への支援と「敵からの反撃」に備えることを目指しています。
表1 01中期防主要兵器整備計画 |
||
区 分 |
種 類 |
整備規模 |
| 陸上自衛隊 |
戦車 |
91輌 |
| 火砲(迫撃砲除く) |
47輌 |
|
| 多連装ロケットシステム |
18輌 |
|
| 装甲車 |
129輌 |
|
| 戦闘ヘリコプター |
10機 |
|
| 輸送ヘリコプター(CH-47JA) |
7機 |
|
| 地対空誘導弾(ホーク)改善用装備品) |
0.25個群 |
|
| 新中距離地対空誘導弾 |
1.25個群 |
|
| 海上自衛隊 |
護衛艦 |
5隻 |
| 潜水艦 |
5隻 |
|
| その他 |
15隻 |
|
| 自衛艦建造計 |
25隻 |
|
| (トン数) |
(約8.6トン) |
|
| 哨戒ヘリコプター(SH-60J及びSH-60改) |
39機 |
|
| 新掃海・輸送ヘリコプター |
2機 |
|
| 航空自衛隊 |
要撃戦闘機(F-15)近代化改修 |
12機 |
| 支援戦闘機(F-2) |
47機 |
|
| 輸送ヘリコプター(CH-47J) |
12機 |
|
| 空中給油・輸送機 |
4機 |
|
陸海空各自衛隊の整備計画は、陸では74式戦車の退役に備えて90式戦車を小型化した新型戦車の開発に取り組み、戦闘ヘリコプターなどを増備します。海では1隻950億円もする排水量1万3,500トンのヘリ搭載型補給艦を2隻建造し、そのうちの1隻はすでに岡山県の三井造船玉野事業所で進水し、「ましゅう」と命名されています。1万トンを超える自衛艦はこれが初めてです。
アメリカのミサイル防衛計画(MD)に組み込まれる7,700トンの新型イージス・システム(ベースライン7)を搭載した護衛艦も2隻建造します。
空では遂に空中給油機が導入(4機)されることになりました。
かつて70年代には政府自身が「周辺諸国の、領海、領空深くはいっていけるものは、許容されざる足の長さ」とし、その保有を認めなかった代物です。
また、現在のC1輸送機の後継機として、その3倍の能力を備えた航続距離6,500㌔、最大積載量約26㌧の大型長距離輸送機の開発も盛り込みました。(表1参照)
部隊編成では、「核・生物・化学兵器による攻撃(NBC攻撃)等各種の攻撃形態への対処能力の向上を図る」ことを決めました。自衛隊は創設以来米軍の指導のもとにNBC戦対処訓練を重ねていますが、アメリカの強い圧力を受けて2000年度予算に24億円の本格的なNBC関連経費を計上し、2001年度はそれを29億円に増額しました。
2000年3月には、東京世田谷区の陸上自衛隊三宿駐屯地にNBC兵器に対処する専門部隊=開発実験団部隊医学実験隊を新たに編成したのを始め、2001年度からは師団・旅団の化学防護隊の強化に力を入れています。
これらの装備・研究開発は、いずれも新ガイドラインのもとでアジア諸国から中東へ海外出動することを前提にして初めてその意味を持つものばかりです。
日本の自衛隊のこのような大軍拡が、朝鮮半島や中国、東南アジアの近隣諸国に大きな脅威をもたらすことになるのはあまりにも明らかであると言わなければなりません。
(2)
アメリカのブッシュ戦略と有事法制
2001年に登場したアメリカ・ブッシュ政権は、全世界で石油を始めとする資源と市場の利権を確保する戦略とともに中国を将来の米国の国益をゆるがすライバルと位置付け、アジアに介入していく戦略を基本にしています。そしてアーミテージ報告などで在日米軍基地強化と日米共同作戦をすすめ、自衛隊を「後方支援」から「戦闘支援」に巻き込む集団的自衛権の行使と、日本全土をねこそぎアメリカの引き起こす戦争に協力させるための有事法制を日本政府に要求してきました。
|
| (写真2-1)アーミテージ報告 「アメリカと日本:成熟したパート ナーシップに向けた前進」 |
(ア)アメリカの「対テロ作戦」と「大量破壊兵器の脅威」
2001年9月11日の米テロ事件後、アメリカは「テロ壊滅」を口実にアフガニスタンを攻撃し、多くの市民に犠牲者を出し、その後もフィリピンをはじめとするアジア各地に介入しています。
ブッシュ大統領は2002年1月に北朝鮮、イラク、イランを名指しで「悪の枢軸」と呼んで敵視し、2003年3月にはイラクに対する国連の査察が進んでいた状況のもとで、国連安保理に米、英、西による対イラク武力攻撃容認決議案を提出し、これに対する支持が得られないと見るや決議案を取り下げ、「大量破壊兵器の脅威」を除去するためと称して一方的にイラクを攻撃しました。
米英軍は、大量のミサイル、爆弾で数千人の市民を含む犠牲者を出してサダム・フセイン政権を倒し、市民生活の混乱のなかで占領軍として現在も居座りつづけています。そして「中東の民主化」と称してイラク近隣国にも脅迫を続けています。
(イ)アメリカの核戦略
アメリカ・ブッシュ政権は、2002年1月の核態勢の見直し(NPR)により、引き続き核独占を維持・強化しつつ新型核兵器の開発、核実験の再開、通常兵器と一体化した使用、非核保有国を含めて先制核攻撃の対象とするなどの方針を打ち出しました。
それに基づき2000年のNPT(核不拡散条約)再検討会議で自国も同意した「核兵器廃絶の約束」を反故にし、CTBT(包括的核実験禁止条約)を無視し、ABM(弾道弾迎撃ミサイル)制限条約を「国益優先」の立場から破棄する一方で、ミサイル防衛構想や新型核兵器の開発を推進しています。
(ウ)アメリカ大統領に「ちぎれるほどシッポを振る」日本の首相
アメリカ政府のあまりにも身勝手な横暴と先制攻撃戦略にヨーロッパの先進国をはじめ世界中から批判が集中しているなかで、日本の小泉首相は米英のイラク攻撃に「信じられないような強い支持」(アーミテージ米国務副長官)をいち早く打ち出し、アメリカの戦闘支援に積極的に応える異常な姿勢を鮮明にしてきました。
政府は2001年末に「テロ特措法」を成立させ、史上はじめて「戦闘地域」に自衛隊を派遣し、派遣期間を半年ごとに延長し、2003年10月にテロ特措法を延長して米軍の戦闘支援を継続しています。
小泉政権は、アメリカのさらなる要求に積極的に応えるため有事法制の骨格となる武力攻撃事態法など有事関連3法を北朝鮮の核開発問題を最大限に利用して2003年6月についに成立させました。
それに続いて、アメリカの言いなりにイラクに自衛隊の地上部隊を派遣しようとする「イラク特措法」を国民の反対を押し切って2003年7月に強行採決により成立させ、イラク全土が戦争状態の泥沼に陥り、2名の日本の外交官が殺される事態になってもなお、自衛隊を何が何でもイラクに送ろうとしています。
さらに小泉政権はこれにとどまらず、北朝鮮の監視を目的とする軍事偵察衛星を打ち上げ、「防衛計画の大綱」を2003年度中に改定して未完成の海上発射型(SM-3)と地上発射型(PAC-3)のミサイル防衛システム(MD)の導入や高度な指揮通信能力を持った「ヘリ空母」型護衛艦の建造をめざすとともに、国際平和協力業務を自衛隊の本来業務に格上げし、恒久的な自衛隊海外派兵態勢をつくるために「国際貢献部隊」を創設させる方針を表明しました。
(エ)戦争反対の世論との矛盾
これらの動きに対して広範な国民から「戦争反対」「自衛隊の海外派兵を許すな」の声が大きくなり、岡山県でも超党派の政党、労働組合、民主団体、青年・女性組織、弁護士、宗教家など広範なひとびとによる「有事法制の発動と海外派兵に反対し、憲法を守る共同行動連絡会」が結成され、ピースウォークや宣伝行動に取り組んでいます。
 |
| (写真2-2)有事法制、自衛隊海外派兵に反対する広範な運動 |
在日米軍基地は海外への出撃拠点基地としての性格をよりいっそう強め、横須賀、佐世保、岩国、三沢をはじめ米軍基地機能の急速な拡大が行なわれるなかで、基地被害が後を絶たない状況です。
岡山県でも県北や県西部での米軍機の低空飛行訓練で住民は大きな不安を感じています。
世界的な米軍再編に伴い、神奈川県や沖縄県に見られるように在日米軍基地の整理統合縮小と称した基地再編機能強化拡大が画策されています。
また、日米地位協定に基づく民間の港湾・空港施設の軍事利用や国内法を無視した勝手な軍事利用が横行しています。
自衛隊はヘリコプターやLCAC(上陸用輸送艇)の多用による敵地攻略型訓練や日米共同訓練を増加させ、「北方機動特別演習」やアメリカ本土での演習のための民間航空や船舶をも使用した海外派兵型長距離輸送訓練や夜間長距離移動訓練、捕虜取り扱い訓練、多国間共同での潜水艦救助訓練や掃海訓練、空中給油訓練など海外作戦を想定した実践的な訓練が行なわれています。
|
| (写真2-3)岡山市内で行なわれた対テロ毒ガス対処訓練展示 |
また、「テロ対策訓練」に名を借りたNBC対処訓練や治安出動訓練を強化し、2003年度内に特殊作戦群(練馬)をつくり、習志野駐屯地(千葉)に対テロ対処の特殊部隊を設置する計画です。
自治体や民間企業が参加する災害対策訓練への介入による有事対処型の訓練を増加させ、行政組織の有事対処や自衛隊の統合運用を押し進めるとともに、周辺事態に対処する日米相互協力作戦計画も調印され、新ガイドラインで示された日米共同作戦態勢の政治・軍事各レベルでの各種協議が進んでいます。
(3)
岡山県内の自衛隊の具体的動き
このような情勢のなかで、岡山県内の自衛隊が、海外出動、本土有事対処、日米共同作戦態勢対応についてそれぞれどのような動きをしてきたかを以下に具体的に検証してみます。
(ア)2001年北方機動特別演習
2001年に実施された北方機動特別演習は、6月19日から8月1日まで陸上自衛隊中部方面隊の第13旅団(司令部:海田市)と第2混成団(司令部:善通寺)の隊員約4,400人と約1,400両の車両、戦車10両、火砲21門が参加し、中国・四国地方から矢臼別演習場へ向けて陸・海・空路で輸送されました。
このなかで、日本原駐屯地の74式戦車と155ミリ榴弾砲が駐屯地を夜中に出発し、水島港から自動車運搬船に積み込まれて名古屋港経由で苫小牧港に陸揚げされ、矢臼別演習場まで運ばれました。
水島港は1994年朝鮮危機の時に米軍から使用を要求された経緯があります。
今回の輸送は、朝鮮半島やアジア各地に自衛隊を派兵するために行われた訓練であり、有事の際には一般道や商業港及び民間の船舶を自衛隊や米軍がわがものがおで優先して使用することを示しています。
この北方機動特別演習での一般道や水島港の利用に対して県内各地から「ふるさとの軍事利用を許すな!」の運動が展開されました。
 |
| (写真3)水島港から自動車運搬船に積み込まれる日本原の74式戦車 |
(イ)
岡山空港の軍事使用
1997年には岡南飛行場に76回もの米軍機が着陸しています。また日応寺の岡山空港にも1995年から1997年にかけて毎年3回着陸していましたが、どちらも1998年からは1機も着陸していません。
(ウ)三軒屋基地等からのPKO派遣
カンボジアPKOでは岡山県警から派遣された高田警視が殉職した痛ましい歴史がありますが、三軒屋駐屯地の施設中隊からは1992年のカンボジアPKOに11人の隊員が派遣されました。
また2002年10月にはゴラン高原PKOに1名が派遣され、2003年2月から山地3佐以下22名が第3次東チモールPKOに派遣されています。また、この第3次東チモールPKOには日本原の第13特科隊からも3名の隊員が派遣されています。
(エ)日米共同訓練
(a)ヤマサクラ37
周辺事態法が公布施行された1999年の12月8日、日米兵站連絡会議のプログラムによる中部方面隊の兵站施設研修の目的で米太平洋陸軍兵站部長・ダニエル大佐以下6人が三軒屋基地に訪れています。
、これには自衛隊側から陸幕装備部副部長や中部方面隊の後方運用課長ら8人が参加しました。
弾薬庫は日米新ガイドライン・周辺事態法などが発動されるとき、兵站作戦の中枢を占めます。
そのときに備えて三軒屋の機能点検が日米双方で行われたと見なければなりません。
このことは訪問の直後2000年1月20日から29日まで陸上自衛隊中部方面隊で行われた日米共同指揮所演習(マサクラ37)で、三軒屋基地が軍事的重要拠点として扱われたことによっても裏付けられています。
米陸軍座間基地のホームページに流出した指揮所演習のシナリオによると「日本周辺で有事があり,それにつけこんで敵軍は南進し、九州と山口県に上陸,第13旅団が応戦したが岡山県の西半分まで攻め込まれ,米本土から名古屋港に上陸した米陸軍第1軍団が撃退する」という内容でした。
(b)日本原演習場
日本原の部隊や隊員は滋賀県の饗庭野(あいばの)などで日米共同演習に参加しており、日米共同作戦に対する能力を次第に蓄積していると見られます。
日本原演習場も全国で広がっている日米共同使用の演習場にならないという保証は全くありません。自衛隊施設の日米共同使用は、日米地位協定二条4項bの規定によるもので、国会も自治体も全く関与できない日米合同委員会の密室協議で決められます。
その数は中曽根内閣時代から急増し、1982年に8カ所であったものが、1999年度末には44カ所に広がりました。
すでに日本原演習場より小さい自衛隊の新潟県高田関山演習場や群馬県相馬原演習場が米軍との共同演習場として使われています。
日本原には終戦後の1946年3月から連合軍が進駐し、1950年に始まった朝鮮戦争下で米軍の激しい実弾演習が行われ、町民が多くの被害を受けた歴史がありますが、新ガイドライン・日米共同作戦体制のもとでその悪夢がよみがえる可能性が非常に強くなっています。
2000年12月の奈義町議会で町長に日米共同演習の受け入れを促す質問が行われたことは奈義町議会始まって以来のことで、その意味を軽視することはできません。
2.県内の自衛隊の現状
県内の自衛隊の各部隊や施設の位置付けと現状を以下に検討してみます。
(1)日本原駐屯地
96中期防で1999年3月29日、定員7,100人の陸上自衛隊中部方面隊第13師団が定員4,100人の第13旅団に改編されました。
第13旅団は、新大綱が目標としている陸上自衛隊8個師団6個旅団の体制を目指して最初に編成替えを行った組織で、「中国地方の特性を踏まえ、地上及び空中機動能力や情報収集機能の強化を図ること」(「99年版防衛白書」)を目的としたコンパクトな「陸上機動旅団」です。
 |
(写真4)日本原駐屯地の74式戦車 |
日本原駐屯地には陸上自衛隊第13旅団の第13特科隊本部、本部管理中隊、特科隊第1~第4中隊、第13戦車中隊、第13高射特科中隊、日本原駐屯地業務隊、第312基地通信中隊日本原派遣隊、第116地区警務隊日本原派遣隊、第421会計隊、駐屯地広報室、岡山地方連絡部地域援護センターなどがあり、現在約740人程度が常駐していると見られます。
配備されている主な武器は、155ミリ榴弾砲(FH70)、81式短距離地対空誘導弾(短SAM)、93式近距離地対空誘導弾(近SAM)、74式戦車、高機動車などで、かつての105ミリ榴弾砲や61式戦車など旧式の兵器は姿を消し、近代化され機動力に富んだ高性能兵器が数多く導入されています。
 |
(写真5)訓練展示中の近SAM、FH70など |
この日本原駐屯地は県内の自治体行事への自衛隊派遣でも重要な任務を負っています。県内自治体の総合防災訓練や2002年1月の岡山県、岡山市、倉敷市の大規模災害対策図上訓練には日本原駐屯地各部隊が派遣されており、まさに岡山県の自衛隊を代表する部隊として位置付けられています。
(2)日本原演習場と防衛施設庁広島防衛施設局津山防衛施設事務所
勝田郡奈義町と勝北町にまたがる日本原演習場は、1,954ヘクタールで、陸上自衛隊の中規模演習場14カ所のうち6番目の広さです。大部分は奈義町に広がり、奈義町の約24%を占めています。
奈義町に届けられた演習の実施計画書によると、日本原演習場は主に中部方面隊の各部隊が使用しており、ピーク時の1997年には年間303日、そのうち実弾演習は延べ127日に及び、演習参加人員も延べ11万人に達しています。
演習場内での実弾の使用総数は98年に約11万発、1999年に約13万2,000発でした。演習日1日平均1,400発に相当する規模です。110㍉個人携帯対戦車弾の演習が急増し、1998年に33回3337発、1999年は25回で4,331発の実弾が発射されています。
勝田郡平和委員会の最近の調査では2000年度1年間に約95,000人の隊員が278日間使用しており,1日あたりの実弾は1,600発に上り、演習の様相も次第に変化しています。ヘリコプターの低空飛行と夜間飛行訓練が増加し、戦車の夜間走行や、防毒マスクを着けた訓練も目撃されるようになりました。
日本原駐屯地にも化学除染装置を装着した車両が配備されています。小銃・機関銃の演習も目立って増えています。しかし、2001年4月以降、自衛隊から地元自治体への「演習通告」に実弾数が記述されなくなりました。軍事機密扱いがあらゆる場面で拡大されつつあります。1996年9月には演習場外の一般道を使った40キロの夜間無灯火行進・有線通信構成及び敵陣地攻撃奪取訓練が行なわれ、2002年5月にも25キロ行進が行なわれています。
 |
(写真6)日本原演習場内の徹甲弾標的用のドーム |
ヘリコプター、榴弾、戦車砲の騒音被害はいっそう激しくなっており、交通事故も相変わらずおきていて住民の不安の声が大きくなっています。
特に1991年12月に起きた完全武装自衛隊員の逃亡事件は周辺住民を恐怖に陥れました。
演習場のある勝田郡勝北町に隣接する津山市には防衛施設庁の県内でただひとつの出先機関・津山防衛施設事務所があり、日本原演習場や基地施設に関する業務にあたっています。
(3)三軒屋基地
岡山市宿の陸上自衛隊三軒屋基地には、三軒屋弾薬庫を管理する関西地区補給処三軒屋弾薬支処に加えて、 第349施設中隊、第312基地通信中隊三軒屋派遣隊、第116地区警務隊三軒屋連絡班が置かれています。1993年2月の防衛庁国会提出資料によると面積は202.5ヘクタールで約250名の隊員がいることになっています。
三軒屋弾薬支処は中部方面隊関西地区補給処(宇治市)の直属部隊で、弾薬の貯蔵と在庫管理、搬入・搬出の業務などにあたっています。
津島平和委員会の調査によると、弾薬庫地区内には戦前から20数ヵ所の弾薬庫があり、さらに1985年ごろ新しい弾薬庫が作られ、2002年度予算でも新しい弾薬庫が作られています。
(写真7-1)弾薬庫入り口の危険度「1」の表示 |
そのうち少なくとも4カ所の入り口に数字の1を表示した八角形のプレート(「1」標識)が立ててあります。
この標識は、米軍に準拠したもので、最も危険な大爆発を起こす火薬類を貯蔵していることを示しています。米国防総省弾薬・爆発物類安全基準によれば、「1」標識の弾薬庫とは、「事故が起きた場合は消火活動に関係ないものは2,000フィート(約600メートル)以上離れなければならない。」ものとされています。陸上自衛隊の「火薬類の取扱いに関する達」(昭和55年)の「火災標識設置基準」でもこの基準が適用されています。
陸上自衛隊は1978年11月のガイドライン以降、1980年月からこの米軍の基準に準じて弾薬庫の危険度を表12示するようになり、三軒屋には1981年1月からこの「1」標識が立てられてきました(岡山市議会1989年3月10日答弁)。
しかし三軒屋駐屯地周辺には、このような爆発の危険を知らされないまま、弾薬庫から500メートル以内に半田山ハイツや津高台団地などの住宅が隣接しています。
第349施設中隊は戦場の最前線に出撃して侵入路や陣地を構築し、地雷を敷設するなどの任務を持ち、これまで3ヵ所のPKO活動に34名の隊員を派遣しています。
 |
(写真7-2)新しくなった三軒屋基地正門 |
第312基地通信中隊三軒屋派遣隊は金甲山に通信施設を設置しています。
この金甲山のアンテナには隊舎から敷地内の山頂にある反射版を介してマイクロ波回線がつながっています。
2001年にはこの通信施設はIDDN(統合防衛デジタル通信網)に組み込まれ、アンテナが変更されています。
三軒屋駐屯地は山陽自動車道岡山インターと国立病院、岡山空港に近く、岡山市街と水島港などにもアクセスがよいため戦略的に重要な拠点になります。
また旧日本軍の練兵場だった県総合グラウンドは有事の際に車両、物資、の集積基地とされる可能性があります。さらに旧陸軍司令部のあった岡山大学は兵員の集積基地として使用される危険もあります。
三軒屋駐屯地ではここ数年立て続けに宿舎や隊施設が建て替えられ、2002年度には新しい弾薬庫が造られるなど機能が強化されています。
有事関連3法が国会に提出された2002年には三軒屋弾薬庫周辺の住民が不安を募らせていたなかで、津高地区から津島、御野、原、牧石の住民らが集まって「有事法制に反対する三軒屋弾薬庫周辺住民の会」を結成し、危険な三軒屋基地の撤去を求めて住民アンケートや学習会、宣伝行動などに取り組んでいます。
(4)
マイクロ波通信施設
備前市福石、和気町木倉、寄島町鉢山の県内3カ所で自衛隊の防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の中継施設が2002年に完成し、IDDNの太平洋側ルートのうち兵庫県赤穂市の黒蔵山中継所(既存施設)→備前市福石→和気町木倉→金甲山(既存施設)→寄島町鉢山→広島県と伸びる岡山県内のルートが出来上がりました。
このIDDNはもともと自衛隊と米軍の相互運用性を基本としているので、その基地の機能は米軍と共用され、周辺有事で米軍が出撃するときの作戦・補給に関する膨大な情報処理を後方で支える役割も果たすため、IDDN無線中継所は明らかにセミ米軍基地というべき危険なものです。
このIDDN建設計画は、前96中期防で引き続き整備を推進するとされていましたが、新しい01中期防では「民間の情報通信技術の発展を踏まえて防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備を完了する」とされました。
 |
(写真8)デジタル化された金甲山無線中継所 |
(5)三井造船㈱玉野事業所と防衛庁契約本部大阪支部玉野契約管理事務所
「わが国には護衛艦、潜水艦などの艦艇メーカーが7造船所、掃海艦艇などの艦艇メーカーが4造船所、それに加えて支援船などのメーカーが20社を超えて存在している」(「世界の艦船」1997年3月号)といわれます。
その中で三井造船㈱は、三菱重工業、石川島播磨重工業、住友重機、日立造船などとともに護衛艦建造のカルテルを形成している造船メーカーです。
三井造船㈱玉野事業所(以下三井玉野)は、1953年の第16特別国会で自衛艦の建造が承認されるといち早く三菱重工業などとともに護衛艦の建造に着手し、以来、日本再軍備を艦艇部門で推進する中心的役割を果たしてきました。
 |
(写真9)進水した大型補給艦「ましゅう」 |
最近は、自衛艦最大級の輸送艦「おおすみ」「しもきた」(8,900㌧)や掃海母艦「ぶんご」(5,700㌧)、潜水艦救難艦「ちはや」(5,400㌧)など、外洋作戦に備えて従来の同型艦を一挙に大型化した艦艇が建造されているのが特徴です。
そしてついに1万トンを超える13,500トンの補給艦「ましゅう」が2004年3月に就航予定で2003年2月に進水し、儀装中です。この補給艦は米海軍とのインターオペラビリティ(共同作戦能力)の強化を目指しており、海外での米軍の攻撃作戦や自衛艦の作戦に対する補給に主眼が置かれたまさに「海外派兵型日米共同作戦態勢」に欠かせないものになることは間違いありません。
玉野・灘崎平和委員会の調査で「おおすみ」と「しもきた」に搭載されているLCAC(ホバークラフト型上陸用輸送艇)の格納庫が造船所内に建設され、上陸訓練が事業所内で行なわれていた事や造船所のすぐ近くに防衛庁の契約管理事務所が置かれたりしていることからも、三井造船玉野事業所の軍需依存体質がいっそう深刻なものになっていることが明らかになっています。
| 三井造船㈱玉野事業所の建造艦艇 ―2003年10月現在― | ||||||||||
| <自衛隊装備年鑑等による> | ||||||||||
| № | 計画年度 | 艦名 | 記号 | 艦番号 | 排水量 (t) | 起工 | 進水 | 竣工 | 型式 | 記事 |
| 1 | 53 | いなずま | D E | 203 | 1,070 | 54.12.25 | 55.08.04 | 56.03.05 | いかずち型 | 除籍 |
| 2 | 55 | しきなみ | D D | 106 | 1,700 | 56.12.24 | 57.09.25 | 58.03.15 | あやなみ型 | |
| 3 | 57 | たかなみ | D D | 110 | 1,700 | 58.11.08 | 59.08.08 | 60.01.30 | あやなみ型 | |
| 4 | 59 | いすず | D E | 211 | 1,490 | 60.04.16 | 61.01.17 | 61.07.29 | いすず型 | |
| 5 | 62 | やまぐも | D D | 113 | 2,050 | 64.03.23 | 65.02.27 | 66.01.29 | やまぐも型 | |
| 6 | 65 | みねぐも | D D | 116 | 2,150 | 67.03.14 | 67.12.16 | 68.08.31 | やまぐも型 | |
| 7 | 67 | ちくご | D E | 215 | 1,470 | 68.12.09 | 70.11.03 | 70.07.31 | ちくご型 | |
| 8 | 68 | みくま | D E | 217 | 1,470 | 70.03.17 | 71.02.16 | 71.08.26 | ちくご型 | |
| 9 | 69 | とかち | D E | 218 | 1,470 | 70.12.11 | 71.11.25 | 72.05.17 | ちくご型 | |
| 10 | 70 | いわせ | D E | 219 | 1,470 | 71.08.06 | 72.06.29 | 72.12.12 | ちくご型 | |
| 11 | 71 | によど | D E | 221 | 1,470 | 72.09.20 | 73.08.28 | 74.02.08 | ちくご型 | |
| 12 | 72 | よしの | D E | 223 | 1,500 | 73.09.28 | 74.08.22 | 75.02.06 | ちくご型 | |
| 13 | 73 | のしろ | D E | 225 | 1,500 | 76.01.27 | 76.12.23 | 77.06.30 | 改ちくご型 | |
| 14 | 77 | いしかり | D E | 226 | 1,290 | 79.05.17 | 80.03.18 | 81.03.28 | いしかり型 | 就役中 |
| 15 | 79 | はまゆき | D D | 126 | 2,950 | 81.02.04 | 82.05.27 | 83.11.18 | はつゆき型 | |
| 16 | 81 | ちよだ | A S | 405 | 3,650 | 83.01.19 | 83.12.07 | 85.03.27 | ちよだ型 | |
| 17 | 82 | せとゆき | D D | 131 | 3,050 | 84.01.16 | 85.07.03 | 86.12.11 | はつゆき型 | |
| 18 | 84 | やまぎり | D D | 152 | 3,500 | 86.02.05 | 86.10.08 | 89.01.25 | あさぎり型 | |
| 19 | 86 | あぶくま | D E | 229 | 2,000 | 88.03.17 | 88.12.21 | 89.12.12 | あぶくま型 | |
| 20 | 87 | おおよど | D E | 231 | 2,000 | 89.03.08 | 89.12.19 | 91.01.23 | あぶくま型 | |
| 21 | 89 | ひびき | AOS | 5201 | 2,850 | 89.11.28 | 90.07.27 | 91.01.30 | ひびき型 | |
| 22 | 90 | はりま | AOS | 5202 | 2,850 | 90.12.26 | 91.09.11 | 92.03.10 | ひびき型 | |
| 23 | 92 | はるさめ | D D | 102 | 4,550 | 94.08.11 | 95.10.16 | 97.03.24 | むらさめ型 | |
| 24 | 93 | おおすみ | LST | 4001 | 8,900 | 95.12.06 | 96.11.18 | 98.03.11 | おおすみ型 | |
| 25 | 95 | ぶんご | MST | 464 | 5,700 | 96.07.04 | 97.04.24 | 98.03.23 | うらが型 | |
| 26 | 96 | ちはや | ASR | 403 | 5,450 | 97.10.13 | 98.10.08 | 00.03.23 | ちはや型 | |
| 27 | 98 | しもきた | LST | 4002 | 8,900 | 99.11.30 | 00.11.29 | 02.03.12 | おおすみ型 | |
| 28 | 00 | ましゅう | AOE | 425 | 13,500 | 02.01.21 | 03.02.05 | 04.03.-- | ましゅう型 | |
| <参考> 艦艇の種別と記号 | ||||||||||
| 艦艇種別 | 記号 | 意 味 | ||||||||
| 護衛艦(中型) | D E | Destroyer,Escort Vessel | ||||||||
| 護衛艦(大型) | D D | Destroyer (イニシャルが1字のときは重複させる) | ||||||||
| 潜水艦救難母艦 | A S | Auxiliary Submarine Rscue Tender | ||||||||
| 音響測定艦 | AOS | Auxiliary Ocean Surveillance Ship | ||||||||
| 輸送艦 | LST | Landing Ship Tank | ||||||||
| 掃海母艦 | MST | Minesweeper Tender | ||||||||
| 潜水艦救難艦 | ASR | Auxiliary Submarine Rescue Vessel | ||||||||
| 補給艦 | AOE | Auxiliary Fast Combat Support Ship | ||||||||
(6)岡山地方連絡部
岡山市下石井の岡山第2合同庁舎内にある岡山地方連絡部は自衛隊員の募集業務や広報を担うだけでなく、あらゆる対外的関係の根回しにも動いています。
予備自衛官等の管理、体験入隊や体験搭乗・航海の企画運営、災害派遣訓練やイベントでの自治体や学校などとの連絡調整など多岐にわたります。
県内にはその出先として岡山、倉敷、高梁の3ヵ所に募集事務所、西大寺に募集案内所、津山に出張所があります。
3.自治体への介入
自衛隊の有事対応を先取りする様々な動きが現れていますが、主に地方自治体との関係でどのような動きがあるかを以下にまとめてみます。
(1)
災害派遣と災害対策訓練
今、全国の自治体は大規模災害対策の基本計画を作成していますが、自衛隊は災害時に自治体が自衛隊へ協力要請をすることを柱とするよう介入を強めています。
また、9月1日の「防災の日」を中心とした全国各地の行事に自衛隊が積極的に参加して市民に「頼りがいある」自衛隊をアピールするよう努力しており、毎年9月始めに行なわれる「岡山県・岡山市総合防災訓練」には、県外の陸上自衛隊第13旅団や日本原の第13特科連隊などが参加し、ヘリコプターからの降下による被災者の搬送などの訓練展示をしています。
2002年1月10日には岡山県・岡山市・倉敷市が参加した「大規模災害対策図上訓練」が開催されました。
あらかじめ陸上自衛隊中部方面隊総監が県庁や市役所に表敬して根回しされたもので、自衛隊の「指揮所演習」を自治体の災害対策訓練に応用したものです。
 |
| (写真10)県災害対策本部に 参加した自衛官(県HPより) |
2002年3月21日付けの朝雲新聞によると、自衛隊側はこの訓練を「13旅団震災対処訓練」と位置付け、次のように報道しています。
訓練は当日朝大規模な地震が発生し県南に被害が出たとの想定で、「駐屯地では速やかに災害派遣部隊の編成、車両への装備品の積載が行なわれるなど、災害派遣出動準備完了の態勢をとり、知事の派遣要請に基づき、駐屯地各部隊は一部が県の計画する大規模災害対策図上訓練に参加。県庁、岡山・倉敷両市役所や岡山市消防局に要員を派遣、指揮所演習、連絡調整訓練、通信訓練などを実施して県防災関係者との連携を図った。」「今回初めて自衛隊ヘリの県庁屋上ヘリポートへの発着も披露、災害時に頼れる自衛隊の存在を強くアピールした。」
 |
| (写真11)第13師団からヘリで県庁 に到着した連絡官(県HPより) |
岡山県消防防災課のホームページにはこのときの様子が写真入で掲載され、第13旅団の連絡員がヘリで県庁屋上に到着し、第13特科隊の「部隊移動訓練」、「自衛隊部隊集積地としてリサーチパークの確保」、「県庁屋上への通信アンテナの設置」の模様や、「状況付与室で迷彩服の自衛官と一緒に働く県庁職員」などが紹介されています。
また、この訓練に際して岡山市では、職員に対して「自衛隊の来庁について」という文書を作成し、市役所の中に迷彩服を着た自衛隊員が初めて入り込んでくることにびっくりしないように次のように呼びかけています。
「岡山市では本庁及び消防局中消防署並びに南消防署に来庁・来署することとなっており、本庁では7階大会議室控え室を使用します。自衛隊の到着時刻については、訓練の想定上(午前8時30分地震発生)、地震発生直後に市内にある陸上自衛隊岡山地方連絡部から隊員が出発しますので、午前9時までには到着されます。併せて、本隊も日本原駐屯地から地震発生直後に出発しますので、当日の交通事情により午前10時から11時には到着するものと思われます。陣容としては、地方連絡部は車輌1台、人員2名、本隊は車輌2台、人員約10名程度ですが、当日、7階フロア、エレベーター、屋上(アンテナ設置)等において制服の自衛隊員を見かけることとなりますので、ご周知いただきますようお願いいたします。」
 |
| (写真12)迷彩服の自衛官と同席する 訓練統制部の県庁職員(県HPより) |
これらのことから次の問題点が浮かび上がってきます。
[問題点1]
自衛隊は災害対処訓練を独自に設定し、一部を自治体の訓練に派遣したとしている。つまり自衛隊の動きは自治体にまったく知らされず、各自治体に派遣された自衛隊はその自治体の指揮下に入らず、あくまでも自衛隊の司令の指揮下にあること。
[問題点2] 自衛隊は知事の派遣要請の前から準備行動をしており、派遣要請に基づく派遣手続きは事実上空文化されていること。
[問題点3] 岡山県内の自治体について、自衛隊側の担当は第13旅団であり、窓口は日本原駐屯地司令となっていること。つまり岡山市にある三軒屋基地は13旅団の管轄でない(弾薬支処は中部方面隊直轄で宇治にある関西補給処の指揮下、施設中隊は宇治の第4施設団の指揮下で第2混成団のある善通寺の施設隊の出先)ので岡山市には出動しないこと。さらに施設中隊はPKO派遣等でほとんど出払っており部隊出動できる状態ではないこと。このことは、実際の地震災害などの場合、派遣要請から日本原の部隊の到着までに相当の時間を要し、道路事情によっては到達できない可能性があること。
[問題点4] 派遣される日本原の自衛隊員は大砲、戦車、ミサイルなどの大規模火器攻撃部隊であって災害時に本当に必要な施設部隊や医療班、治安部隊などはいないこと。ヘリコプターは山口県防府、ヘリ降下レンジャー部隊は第8普通科連隊(米子)にたよっていること。海上・航空自衛隊部隊との連携もないこと。
集中豪雨や山林火災などの場合と違って実際の大規模地震災害などの場合には自衛隊は初動で役に立つ保障はないし、部隊が派遣されたとしても現実には自治体の指揮下には入らないし、岡山県内には災害救助や復旧に実際に役に立つ部隊がもともと存在していないことなどがこの訓練を通じて明らかになりました。
 |
| (写真13)岡山市の災害対策本部、左端 窓際が自衛隊の連絡員(岡山市HPより) |
また、三軒屋基地は岡山市の防災無線を設置しており、災害時には頼りになるどころか危険物貯蔵施設としてお荷物になると位置付けられていることが明らかになりました。
さらに、こうした自治体への災害訓練名目での介入は、自衛隊側から見れば有事態勢下での自治体統制の準備訓練として位置付けられていることもいっそう明らかになりました。
自衛隊側から自治体には情報が一切提供されないにもかかわらず、自治体側は災害訓練で何はともあれ自衛隊派遣要請の手続きと集積地の確保を最初に行なう訓練をし、「そばにいてくれるだけで心強い」(災害対策本部での萩原岡山市長の発言)などという実態とかけ離れた認識のもとで、岡山市は2002年度に防災基本計画を見直し、自衛隊への派遣要請、災害時の作業場所(有事における陣地)などの構築をより具体化した基本計画に修正しました。しかし、災害時にもっとも必要になる民間通信、給水、下水処理、食糧、医療品、毛布、テント、入浴施設などの供給態勢の強化が自治体の責任として位置付けられているとは言えません。
(2) 不発弾処理
1999年10月に寄島町沖の海底から引き上げられた機雷や2003年7月11日に岡山市の山上一般廃棄物最終処分場で発見された不発弾は京都桂駐屯地の第103不発弾処理隊が処理しました。こういう部隊こそ「頼りになる自衛隊」といえるのですが、岡山県内では自衛隊三軒屋基地に弾薬支処があっても不発弾処理隊はいません。
(3)自衛隊員募集業務
1996年ごろから岡山市、倉敷市などの広報誌に自衛官募集案内記事が掲載されるようになり、岡山県のホームページにも自衛官募集のページができています。また、県内の各募集事務所も強化され、しつこい勧誘の苦情も寄せられています。
全国的には自衛隊が自治体に対して自衛隊員の募集に適格者かどうかを判定するために必要な住民情報を特別に提供し、さらに採用予定者の身元情報を警察が調査していた例があることが指摘されていますが県内での実態は明らかではありません。
(4)自衛官等の自治体職員への採用
岡山県は大地震などの災害に対する危機管理体制を強化するため、2002年10月12日退職の自衛隊幹部OBを同10月15日付けで県消防防災課防災担当参事(課長級:危機管理監)に採用しました。
中国地方では広島県が自衛隊OBを非常勤で、鳥取県が現職自衛官を出向で危機管理担当職に採用していますが、防災・危機管理担当の常勤の正規県職員として自衛隊OBを採用しているのは岡山県だけです。
このうち、石破防衛庁長官の地元の鳥取県では2003年7月9日に全国に先駆けて「自治体版有事マニュアル」を策定し、引き続き「民間版有事マニュアル」の作成に取り組んでいます。
岡山県では2003年9月5日に県警と陸上自衛隊が有事の際の治安出動を想定した共同図上訓練も実施しています。
(5)有事態勢推進のための自治体介入
岡山県は2003年9月にテロ対処のための県内市町村代表者をあつめたプロジェクトチームを発足させました。これは「国民保護法制」の具体化に向けた有事体制の推進に他なりません。
また、2003年の9月議会に向けて県内のほとんどの自治体に対していっせいに「防衛庁の省昇格を求める陳情・請願」が提出され、11の自治体で採択されています。
(6)自治体の側からの主体的協力
(ア)玉野市の自衛艦入港歓迎式典
玉野市は三井造船玉野事業所の城下町という性格から、三井造船が自衛隊依存体質を強めればそれだけ玉野市政に対する自衛隊の圧力が大きくなっていき、最近は自治体の側から自衛隊に積極的に協力する姿勢もあらわれています。
これまでも宇野港は艦艇修理などで護衛艦が多く見られるところでしたが、2002年からは海上自衛隊艦船があいついで田井新港に寄港し、一般公開や体験航海を行なうようになっています。
2002年2月には練習艦隊4隻の入港と一般公開に対し、玉野市は入港歓迎式典を行い、市のホームページで大きく取上げました。
これまでも市のみなとまつり「マリンフェスタ」などの行事に掃海艇の一般公開が行なわれたことはありますが、まったくの自衛隊の行事に市が歓迎・協力・支援する異常な事態が起こっています。
このほかにも自衛隊員募集業務の一環として体験航海などが行なわれています。
 |
| (写真14)一度に4隻が入港して行なわれた一般公開 |
(イ)玉野市の自衛艦のごみ無料処理
2002年9月11日に玉野市田井の田井新港でおこなわれた海上自衛隊輸送艦「しもきた」の一般公開後、自衛隊からの依頼で「しもきた」のゴミを玉野市が無料で回収・処理をしたことがわかりました。
玉野市の見解では「イベント」ということで市の減免規定を適用して無料にしたという事ですが、イベントであっても自衛隊の事業活動であり、自衛隊からのゴミは事業ゴミとして正規の手数料を徴収するが当然です。
これに対して地元の「玉野・灘崎平和委員会」(垣内雄一会長)は10月3日、市に対して申し入れをおこないました。
垣内会長は、「市主催のイベントであればともかく自衛隊単独の行事まで減免するというのは行き過ぎで、しかも回収されたゴミ量は830キロで、イベントだけでなく航海中のゴミも含まれている可能性が高い。自衛隊はゴミを自ら処理する資格を持たないため、正規の手数料を払って業者や自治体に委託するのが当然だ」と話しています。
(ウ)岡山市の新採用自衛官激励会など
岡山市ではここ数年毎年3月に自衛隊入隊予定者を市長室に招待して激励会を開催し、記念品を渡して激励の言葉を述べています。
さらに2003年6月には天満屋の地下ギャラリーで開催された「ふれあい防衛展」に岡山市長が出席し、テープカットを行なっています。
 |
| (写真15)2003年3月岡山 市長室での新入隊員激励会 |
4.自衛隊の教育や地域への介入
(1)地方連絡部による自衛隊生徒募集活動
2002年倉敷市内の中学校23校すべての学校に自衛隊広報官が来校し、自衛隊生徒募集案内文書を教職員に手渡し、そのうち8校で3年生生徒全員に学校で自衛隊生徒募集案内が配布されたことがわかりました。
1978年のガイドライン以後「広報くらしき」に自衛隊生徒募集の記事が掲載されたときに、県職業安定課から「中学校卒業予定者を対象にした文書による求人活動は禁止されておりルール違反。自衛隊生徒は進学でなく就職にあたる」と指摘されていたものです。
自衛隊生徒募集については1994年にも自衛官が制服で中学校に押しかけて募集ポスターを貼る事件を起こし、世論の厳しい批判を浴びていた経過もあります。
(2)各種イベントの開催
各自衛隊駐屯地が創立記念行事などを企画して訓練展示などを一般公開をするだけでなく、盆踊り大会やチビッコヤング大会、基地見学会、青少年防衛講座、お花見会、わらび狩りなど様々なイベントが開催されています。
また自衛艦や航空機を民間港・空港に停泊・飛来させて一般公開や体験搭乗をさせて自衛官の募集に利用しています。玉野市の田井新港では2002年9月までに自衛艦の一般公開が4回もおこなわれており軍港化への懸念が広がっています。この他にも自衛隊は地域の祭りやイベントに音楽隊を派遣したり車両や自衛艦を展示し、災害派遣のパネル展示や自衛官募集コーナーをつくっています。
4月 |
27 |
日 | 百間川フェスタ(岡山市) | 指揮通信車(展示) |
5月 |
31・1 | 土日 | 玉野みなとフェスタ | 音楽隊(陸)演奏、護衛艦まつゆき、指揮通信車展示 |
6月 |
4-9 | 水 -月 |
航空自衛隊CH47体験搭乗(岡山空港) 「ふれあい防衛展」(天満屋地下) |
|
| 海上自衛隊HSS-2B体験搭乗(岡南飛行場) | ||||
| 20・21 | 海上自衛隊護衛艦体験航海(田井港) | 潜水艦はやしお一般公開、体験航海 | ||
7月 |
総社サマーコンサート | |||
11 |
金 | 岡山シンフォニー(岡山市) | 音楽隊(海)演奏 | |
8月 |
2 |
海上自衛隊US-1体験搭乗(岡山空港) | ||
| 夏休みチビッコ・ヤング、防衛講座(日本原) | ||||
| 桃太郎祭り(岡山市) | 音楽隊(陸)演奏 | |||
10月 |
4 |
土 | 日本原駐屯地創立記念行事(岡山県) | パレード、模擬戦 他行事 |
11月 |
2 |
日 | 津山ふれあいコンサート(ベルフォーレ津山) | |
9 |
日 | 三軒屋駐屯地創立記念行事 | ||
2月 |
15 |
日 | 井原市市政50周年記念コンサート(井原市) | 音楽隊(海)演奏 |
(3)スポーツ大会等での介入
柔剣道大会やマラソン大会など日ごろから訓練をしている自衛隊員が参加し、部隊としても最大限に応援しています。
5.自衛隊の企業への介入
(1)予備自衛官等の制度整備
自衛隊OBで民間企業で勤務するかたわら年間5日間訓練する予備自衛官と、年間30日の訓練を受ける即応予備自衛官、自衛隊経験がなく民間で勤務しながら年間50日の訓練を受けた後に予備自衛官として登録される予備自衛官補制度など各種制度が整備されてきました。
日本原駐屯地では予備自衛官の特科部隊や戦車小隊が編成され、三軒屋基地でも予備自衛官の訓練が行なわれています。
(2)体験入隊(新入社員教育)
新入社員教育などで自衛隊への体験入隊をさせる企業があります。
三軒屋基地では毎年両備グループやチボリ・ジャパン社、スバル自動車など数社が実施しています。
また、最近は新設の中高一貫校で「あたらしい歴史教科書をつくる会」の教科書を採用した加計学園も実施しています。
6.戦争への道と平和の道
以上見てきたように、今後自衛隊の本務としての海外派兵が進められると同時に有事態勢が強化されるなかで、各自衛隊部隊は、海外(周辺)米軍支援任務と同時に本土防衛・治安維持任務を持つことになります。
そして、日本原駐屯地の部隊は自治体を管理、動員する任務も与えられていることが明らかになりました。
また、三軒屋駐屯地の弾薬支処部隊は自衛隊への弾薬供給任務とともに、海外(周辺)米軍支援のための弾薬供給任務(米軍弾薬庫の補完)を持たされる可能性があり、第349施設中隊は引き続き海外派遣任務を中心に持たされる可能性が大きいと言わざるをえません。
(1)有事の場合のシュミレーション
周辺事態下で宇野港は自衛艦や米艦船の修理・補給・乗組員の休養基地として使用され、水島港は車両、弾薬、武器、兵站物資の積み出し、故障車両、負傷兵等の陸揚げ港として使われることが予想されます。
さらに岡山市の総合グラウンドは岡山空港や水島港に向けた物資の集積基地、国立病院は傷病兵の治療に使われ、日本原演習場は日米共同訓練場として使用される恐れがあります。
青江の日赤病院は周辺事態下では医療スタッフが海外派遣されて機能が麻痺する恐れがあり、県庁や各市役所のホールは迷彩服の自衛隊員が占領して指揮所になる可能性があります。
これだけの任務をこなすには今の自衛隊の人数では少なすぎる事態が予想され、予備役の招集はもとより、自治体職員や町内会組織などを大量に動員する必要があります。
そのために日常的な(平素からの、平時での)訓練が行なわれることになります。
(2)人命と生活の安全優先の災害対策
自衛隊の災害派遣はあくまで平時のことであり、いったん周辺事態になれば予測事態が発動され、災害派遣などは吹っ飛んでしまいます。
こんな自衛隊を防災計画に組み込むことは住民の安全に責任を持った計画にならないことを意味しています。
住民の安全をまもろうとするならば、人殺しが本来の任務である自衛隊をなんとか使おうと考えるのではなく、災害時や感染症の流行に備えた住民の生命とライフラインの確保のために日ごろから計画的に重層的な対策をとり、軍事費に使うお金を通信、消防、警察、保健所の強化にまわしていくことが大切です。
ヘリコプターなどの航空機の維持には大変なお金がかかるものですが、海上保安庁や警察・消防などに航空支援のための予算を配置し、自衛隊のヘリコプターや哨戒機、救難機などの自衛隊の機材を改造して捜索・人命救助・消火などの民生用に役立てていくことも検討すべきです。
また、緊急時には軍事通信用の周波数の開放や携帯型通信機と非常用食糧、毛布、テントなどの資材を学校、公民館や病院、町内会集会所などに配置するなどの細かい対策が必要です。
(3)安全を脅かすもの
そしてなにより、他国を核兵器で脅して常に敵を作り上げ、世界に戦争の火種を撒き散らして武力で脅迫しているアメリカに従属依存した安全保障の体制を根本的に改めることが重要です。
軍事力によらずにあらゆる国と仲良くしていくための外交努力、民間経済文化交流、災害・医療・教育支援に力を入れていくことが求められています。
このまま対米従属を続けるなら多くの友好国を失い、経済的にも大きな損失を被ることになります。
在日米軍には日本本土を守る部隊も米軍基地を防衛する部隊もありません。
米軍はアジアや中東諸国に攻撃を仕掛けるための出撃基地として在日米軍基地を使用しています。
近くにはグアムに米軍基地がありますが、日本の「思いやり予算」などで日本に基地を置いたほうが安上がりで様々なサービスが受けられることが魅力になっています。
佐世保や横田では周辺有事の際に米軍家族をいっせいに避難させる訓練を繰り返し行なっていることは、米軍基地が一番に攻撃される危険があることを証明しています。
(4)敵をつくることによってつくりだされる「有事」
新ガイドラインによって自衛隊は本土防衛と治安出動だけでなく海外で米軍の兵站支援を行なうことになりました。
テロ特措法にもとづきアラビア海で米英艦船に給油をしていた海上自衛隊艦艇は実はアメリカのイラク攻撃の支援をしていたことが明らかになっています。
イラク特措法では陸上自衛隊地上部隊が米英占領軍の占領支援・兵站支援を行なうことになります。
すべてがアメリカの言うままに自衛隊の対米支援を拡張してきた自民党政権ですが、小泉首相は自分から進んでアメリカの核の傘の中に入り、アメリカの核戦力の継続を要求し、その代りにアメリカの戦争を支持し、自衛隊を何が何でも戦地へ送ろうとしています。
アメリカと日本政府は「北朝鮮の危機」を最大限に演出し利用して、その実アジアへの出撃拠点としての在日米軍基地の強化と日本の自衛隊の海外派兵体制・有事体制を強化しています。
21世紀に入ってアメリカの強引な先制攻撃戦略に対して多くの国から反対の意思表示が示され、国連加盟国の7割を非同盟諸国が占める国際情勢のなかにおいて、唯一の被爆国である日本がアメリカの核戦略に積極的に協力し、国際法や国連憲章を無視するアメリカの戦略に無条件に強い賛成を表明して世界から孤立する日本の異常な姿勢を一刻も早くやめさせ、日本が憲法9条と非核三原則を世界に広めるために努力する国になることが必要です。
[追加情報]